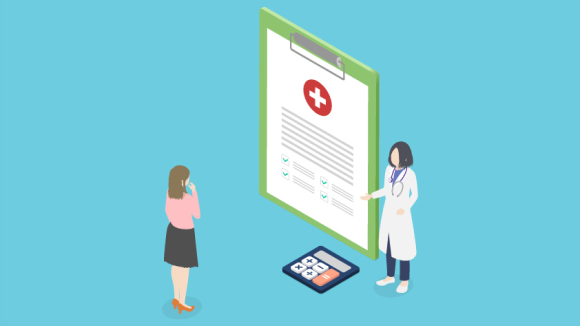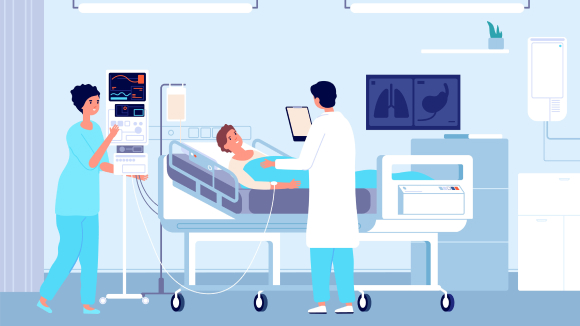「薬の量は多ければ多いほど良く効く、副作用がない範囲では」という概念は、薬理学が発展してきた一世紀以上も前から現在まで、なんの疑いもなく信じ込まれてきたドグマです。
科学的には(いや、ヒトでいきなり実験はできませんので、より正確にいえば、「細胞や動物を使用した実験的には」、というべき実態がありますが)、立派な用量・反応(効果)曲線が描けるからです。
抗がん剤の世界も同じだ、だから副作用で耐えられなくなるギリギリまでの用量(最大耐用量といいます)を先ず探し出し、臨床試験で用量・反応(効果)関係を確かめて、そこから安全域をとって少し下げた用量を推奨(標準)用量として、新薬として世に送り出す、という方針が世界中で採られています。
しかし、本当にこれが正しいのでしょうか?
6月9日着信のASCO(アメリカ臨床腫瘍学会)のニュースでは、前ASCO会長を含めたグループが今年のASCO2017で秘密会合(closed door meeting)を開き、前立腺がん治療に使われるザイティガ(Zytiga、アビラテロン酢酸エステル)の投与量は、実は1/4に減らしても同じように効くのだ、と発表したそうです。
原ニュースは6月8日のワシントンポスト紙です。
→ https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2017/06/08/how-these-cancer-doctors-plan-to-reduce-patients-drug-costs-without-touching-prices/?utm_term=.3df6e3dac8b6
ASCOは毎年3万人以上ものがん治療関係者が参加する巨大な学会だけに、製薬メーカーのスポンサーシップがなければ成り立たないのですが、ここで、薬の使用量を下げようという製薬メーカーの意向に反する意見交換会の開催は、配慮が必要だったのでしょう。
ザイティガは月に$9,400(約103万円)もかかる高額医薬品です。患者は毎朝これを飲まなければなりません。前立腺がん患者が多い米国では、製薬メーカーにとってまさにドル箱商品となっています。
しかし、あまりにも高額なため“financial toxicity”(患者の財政破たん)が発生します。患者だけではなく医療関係者間でも問題視され、投与量減量のために今回の会合開催にいたったというわけです。
従来のドグマに従えば、当然のことながら「減量すれば効果は下がる」、しかし「副作用は減るだろう」と考えられます。
ただし、もし「減量しても効果は下がらない」しかも「副作用も減る」ならば、患者にとっても医師にとってもwin-winの関係となります。今回の発表では、ザイティガを、朝の空腹時ではなく朝食をとりながら服用させた、としています。つまり、飲み方を工夫すれば用量は1/4に下げても大丈夫だというわけです。同様に他の抗がん剤でも工夫次第で用量減量は可能なはずだ、このことが今回の会合で得られた大きな成果だ、と報じられています。
このニュースに接して、筆者は、従来の「用量・反応曲線」ドグマはがん免疫療法の臨床では必ずしも正しくはないのではないか、と気がつきました。
ヒト臨床で用量・反応関係を精密に探るのは、ヒトは体も遺伝子もバラツキが大きいため、すべて一卵性双生児のような均一な実験動物集団とは違って非常に難しいのです。まして初期の臨床試験(Phase IやPhase IIa)では、出来る限り少数の患者数で試験されますから、バラツキの影響は無視できません。その上、がん免疫療法では、単一の免疫チェックポイント阻害剤(抗PD-1抗体)でも、効果と安全性に関して、非常に大雑把な用量・反応関係はあっても、きれいな「用量・反応曲線」が出にくいこと、ごく少量でも安全で良く効いた例が出
ることも判明しています(Ref.1)。
その点を演繹すれば、治験という限られた状況に閉じ込められた特定の患者集団で成り立った用量・反応関係から導きだされた標準用量(と推奨されている量)が、治験に参加しなかった別の個人でも正しく当てはまるとは限らないのです。
すなわち、従来型抗がん剤の場合でさえも、最大耐用量に近い程、効果も上がるのか、と問えば、患者一人ひとりで違う、という答になります。患者によっては、標準用量よりも少量で非常に良く効いた、という例は、従来型の抗がん剤でも実際にでています。
本来がバラバラな特性を持つ患者一人ひとりに、最適な用量をそれぞれに探し出して投与すべきなのです。そしてその探索能力こそ、臨床現場における「医者の腕」と言うべきものだと思います。
Reference
1.Topalian SL, et al. Safety, Activity, and Immune Correlates of Anti?PD-1 Antibody in Cancer. N Engl J Med 2012;366:2443-54.