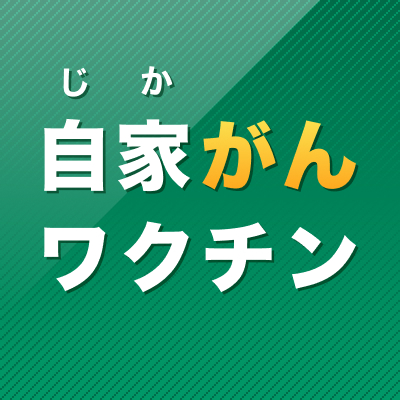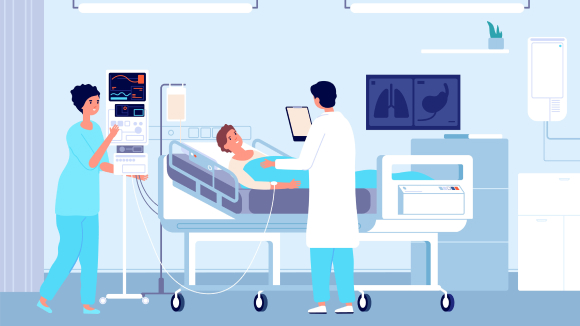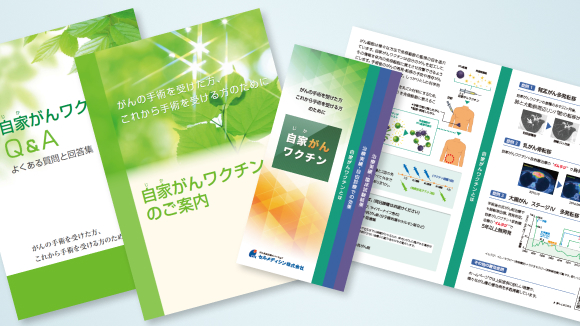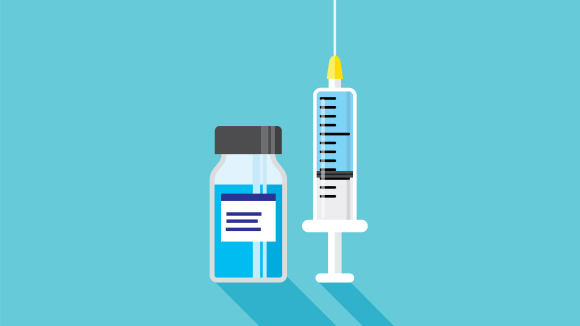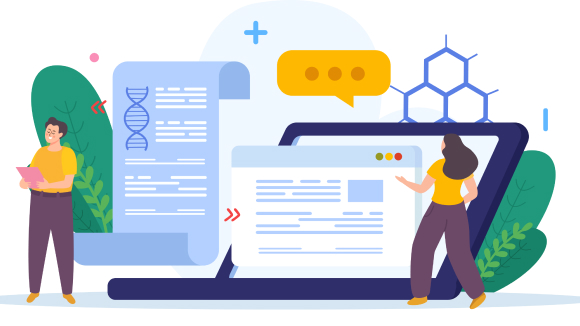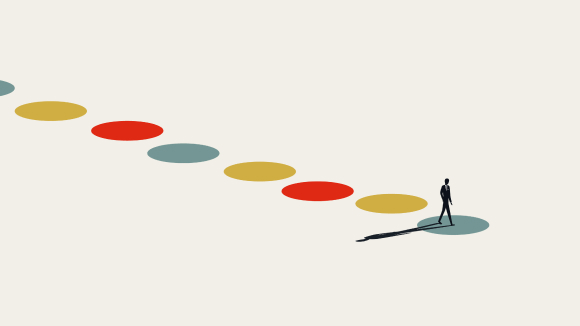現在進行中の膠芽腫(脳腫瘍の一種)に対する公式の医師主導第III相治験、
「Cellm-001による初発膠芽腫治療効果無作為比較対照試験」 (登録番号:jRCT2031200153)
につきましては、セルメディシンニュースNo.638にて「新規症例登録の受付を終了、2年間の観察期間に入りました」とお知らせ申し上げました。
Cellm-001は、弊社の「自家がんワクチン」の脳腫瘍版の開発番号です。
これに関連して、東京女子大・筑波大を中心とする全国14大学の脳神経外科と弊社の他、今回の治験に直接貢献されている先生方が共著者となった、治験の詳細方法(プロトコール)を記述した論文がこの程出版されました(Ref. 1)。
プロトコール論文は、治験の結果が出る前であっても、臨床医学分野ではよく発表されます。
その理由を生成AIに聞いてみると、以下のような回答がありました。
1. 透明性の確保: 研究の目的や方法を事前に公開することで、後からデータを都合よく変更することを防ぎます。
2. 研究の質の向上: 研究デザインが適切かどうかを専門家が評価できるため、より信頼性の高い研究が行われます。
3. 倫理的配慮: 被験者の安全を確保し、倫理的に適切な研究であることを示すために、事前に審査を受けることが求められます。
4. 資金調達や協力の促進: 研究計画が明確であれば、資金提供者や共同研究者を募りやすくなります。
日本では、慶應義塾大学病院の臨床研究推進センターなどがプロトコール作成の手引きを提供しており、多施設共同臨床試験などで活用されています。また、日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)もプロトコールマニュアルを定期的に改訂し、最新の規制や要件に対応しています。
プロトコール論文の作成は、研究の信頼性を高めるための重要なステップとして知られています。
今回の出版も、現在進行中の公式の医師主導第III相治験の着実な進捗状況の一端を示しています。
Reference
1.Muragaki Y, Ishikawa E, Tamura M, et al.
A randomized, placebo-controlled phase III trial of an autologous, formalin-fixed tumor vaccine
for newly diagnosed glioblastoma: trial protocol.
Japanese Journal of Clinical Oncology, hyaf078, https://doi.org/10.1093/jjco/hyaf078 Published: 16 May 2025
~~~△▲~~~△▲~~~
より長く生きられるという安心感を!
You Tubeで【自家がんワクチンとは】をご覧ください。
~~~△▲~~~△▲~~~