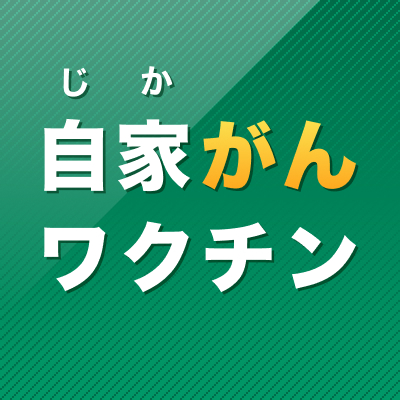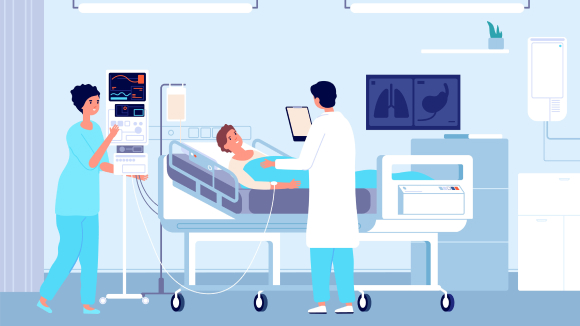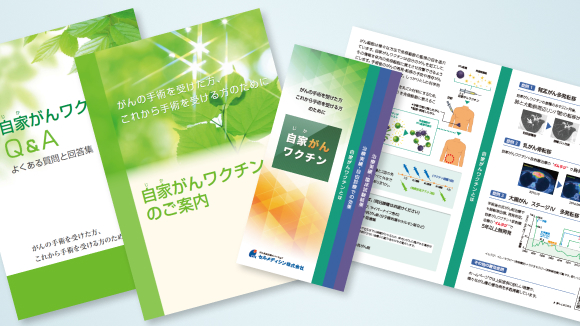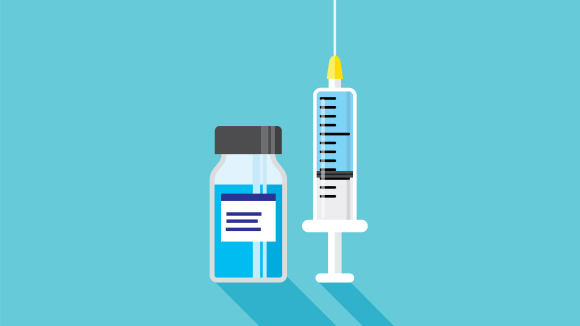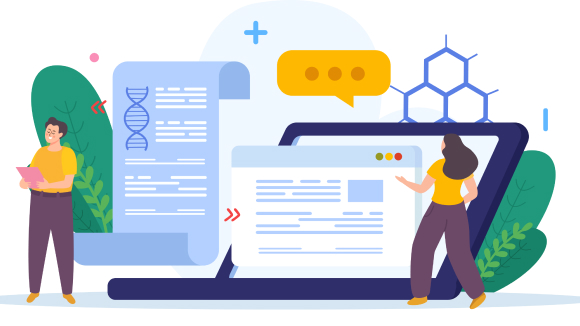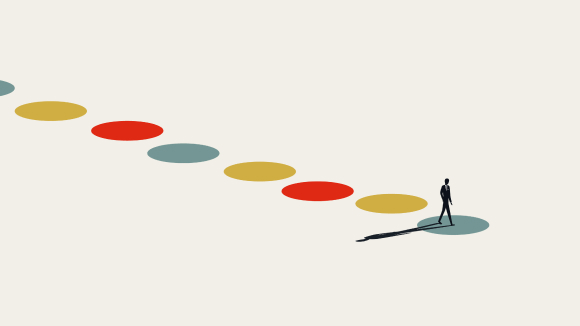先週7月8日に
・トピックス No. 649「達成!世界新記録:“自家がんワクチン”、転移した乳がんで世界最長の延命効果を示す – プレスリリースを発信しました」
を出しましたが、今回はその続きです。プレスリリースの根拠論文は、今回の文末に再録してあります (Ref. 1)。以下、ちょっと長話になりますが、ぜひお読み願います。なにしろ、50億円くらいの節約ができます、という内容ですから。
さて、前回のプレスリリースでは、
広島県尾道市の医師グループは、ここ35年来、尾道市領域で手術を受けた乳がん症例(総数n=698)の予後を、日常診療のカルテ記載のデータ(実臨床データ)を基にして、丁寧に追跡調査してきておりました。
~(中略)~
実臨床データを、重要な患者背景因子ごとに丁寧に切り分けて、
・どの因子が本当に役にたっているのか
を検定する統計学的な解析方法があります。過去の実臨床データをあたかも「これから臨床試験を行うがごとく」に見立て、一つの注目因子(薬剤)の臨床効果を検定する方法が、ターゲットトライアルエミュレーション法
です。
(効果の有無が決定できる標的となる臨床試験を模倣した試験法)
と記載しました。
ここでいう「ターゲットトライアルエミュレーション法」とはどんな解析方法かを今回は説明しましょう。
(かく言う筆者は統計学は素人同然です。自分で理解できる範囲しか書けないことを、あらかじめご了承願います。もし統計学に詳しい読者で、以下の説明に間違いを見つけられたら、メールでのご指摘を歓迎します)。
がんの臨床試験では、新薬の効果が確かにあると証明できる方法として、「無作為化比較対照臨床試験(randomized controlled clinical trial, RCT)」が用いられます。これが狙いの(ターゲットとなる)試験(トライアル)と理解していただければ良いかと思います。
RCTでは、試験に参加してもらう患者さんをランダムに(無作為に)振り分け(昔はサイコロを振っていましたが、今はコンピューターをサイコロ代わりにしています)、
・一方に比較に使う対照薬(ときには偽薬)
・他方には試験したい新薬(実薬)
を投与し、それらの効果(例えば、亡くなるまでの生存期間)を観察していきます。
ランダムに振り分けると、2つに分けた患者群の背景因子(例えば、年齢分布、男女比、等)もランダムに分けられてしまいます。その時、背景因子にバラツキがあるとしても、それぞれの群の患者数が多ければ、コンピューターを用いてうまく振り分ければ、平均値がほぼ同じになるように分けられます。
そうすると、背景因子が同様で、対照薬か実薬かの違いだけがある2つの患者群が出来ます。
もし、対照薬と実薬の間で、薬の効果に差があれば(効果を生存期間で測ったときは)、薬の投与後、現在から将来に向かって観察を続けていけば、対照群に比べて実薬群の方々が、はっきりと長生きしていくことがわかります。
しかし、この方法には欠点があります。もし対照薬が患者さんの病気に対して無効(か効果が弱い)なら、対照群に割り付けられた患者さんは損をします。
そのため、あらかじめ対照群に割り付けられたとわかると、患者さんは皆、臨床試験から逃げ出してしまい、試験自体が成立しなくなります。
そこで、一般的には、どちらの群に割り付けられたかは患者さんには隠して試験を進めます(盲検試験といいます。患者さん担当の主治医にも割り付けがわからないように隠す場合は、二重盲検試験といいます)。
その臨床試験の終わりがくると、どちらの群に割り付けられたかを開示して(キーをオープンにして)、患者さんごとに対照群だったか実薬群だったかを分類すれば、2つの群の間で、生存期間に差があるか否かを比較できます。
このとき、差があまり大きくなく微妙なときでも、数の多い患者数を頼りに、統計学的に比較すれば、実薬の効果があるかないかが判ります。
しかし、この方法(RCT)は、現在から将来に向かって試験を進めるため、生存期間を比べる場合は、病気がタチの悪いがんであっても、長い時間(普通は数年以上)がかかります。
それだけ臨床試験のコストも跳ね上がり、患者数が多い場合は、一つのRCTで数十億円もかかることがよくあります(がんなら1回の正規の試験=治験で50億円かかるのが相場というところでしょうか)。
「これじゃあ、たまらん」、と考えて工夫されてきたのが、ターゲットトライアルエミュレーション(TTE)法です。
エミュレーション(emulation)とは、本来は負けまいと張り合うことを意味し、実際には、相手を模倣して対抗するという意味になっていますね。
このTTE法では、過去の臨床データを使います。
過去に、既に(当時の新薬の)治療を受けた方と、受けていない(対照群に当てはまる)方の予後を比較するのです。
過去のある時点を起点に設定し、そこから現在に向かってくる時に観察されたデータ(例えば生存期間)を測定すると、過去の観察期間が非常に長くても(例えば30年もかかったとしても)、既に手元に臨床データがありますから、統計解析もすぐにできることになります。
当時の新薬が今でも効果の評価が未定の新薬状態のままになっていて、TTE法で効果がわかるなら、楽なものですよね、50億円節約できるかもしれないのですから。
ただし、やはりこの方法にも欠点があります。
過去の新薬(実薬)群に丁度対応する比較対照群にあたる患者さんを選ぶとき、うっかり適当に選んでしまうと、両群の患者さんの背景因子に大きな偏り(バイアス)が入り込んでしまい、背景因子のバランスがとれた群の間の比較ができない、という問題が生じるのです。
いわば「ご都合主義の色メガネで患者さんを選んだのだ、だからあたかも実薬が効いているように見えるのだ」、と批判されても反論できません。
そのために、患者さんを選ぶ方法を、上記のランダム化試験(RCT)に参加する患者さんに適用する「選択基準」と同様の「選択基準」を設定して、過去の患者さんを選ぶという方法をとります。
同様に、その他の試験条件についても、RCTのやり方をできるだけ“模倣した”試験条件を設定します。
これによって、ご都合主義の色メガネを排除するのです。
その上で、選ばれた実薬群と対照薬群の間の背景因子のバラツキに大きな偏りがない、ということを、主な背景因子ごとに検定しなければなりません。
これは結構面倒な作業です。実薬の効果に影響する背景因子は何かがはっきり分っていれば(例えば年齢)、その背景因子がそろう患者群を選べば良い(平均年齢がほぼ同じになるように)のですが、
影響する背景因子は何かが分っていない場合は、仕方がないので、患者さんの生活背景がなるべく均質な集団を対象にするのが得策です(一方の群が肉食集団で他方の群が菜食主義者ばかりだ、というようなことが起こらないからです)。
このような理由で、今回の「ターゲットトライアルエミュレーション(TTE)法」による実臨床データの解析では、
広島県尾道市域の乳がんの患者さんで、手術を受けた方々698例のうち、手術後にどこかの時点で遠隔転移が検出されステージIVに入った患者さん群(97例)を試験対象にしました。この方々で、遠隔転移が検出された日を、今回のTTE法による解析の起点に設定しています。
つまり、過去の起点に立ち返ってみれば、これからランダム化試験(RCT)を開始するのとよく似た試験になるように、条件設定したというわけです。
ただし、本来のRCTとの決定的な違いは、選ばれた患者さんひとり一人について、実薬群か、対照薬群かについて、あらかじめ判明しているという点です。
(このため、ご都合主義の色メガネを完全に払しょくしている、とは言えない状態が残ってしまいます。)
特に、重要な背景因子については、実薬群と対照薬群の間に大きな偏り(バイアス)はないことを示さないといけません。
さもないと、 「年齢が若い実薬群と高齢者が多い対照薬群では、年寄の予後は短いのだから、実薬群が長生きしているからといって、本当は何も効いていないのに実薬が効いているというのは、間違いだ」ということになりかねません。
そこで、今回のTTE法による解析では、(実薬に設定した)自家がんワクチン(AFTV)の他に、
重要な背景因子として、放射線治療(RT)、ホルモン療法(HT)、化学療法(Chemo)、乳房全摘
(Mastectomy)に着目しています。
他に、年齢、遠隔転移検出前の最初の手術時の乳がんのステージのバラツキ具合、最初の手術時の際の乳がん固有のサブタイプの分布、乳がん転移先の臓器の種類の分布も調べましたが、統計学的にみて、両群には、有意差を示す大きな偏りはありませんでした。
また、重要な背景因子のなかでも、化学療法(Chemo)、乳房全摘(Mastectomy)では、やはり両群には、有意差を示す大きな偏りはありませんでした。
結局、重要な背景因子として残ったのは、RT、HTでしたが、RTはAFTVが投与された多くの方で併用されていること、そして
・自家がんワクチン(AFTV)
・放射線治療(RT)
上記の治療法の併用は「相乗効果がある」ことを、実臨床データから掘り出すことができたのです。
そして、HTは、初回の手術から遠隔転移検出(起点)までの間に投与しているととても良く効くが、遠隔転移を起こしてしまうともう効かなくなること、一旦は背景因子から除外したChemoは、実はむしろ、AFTVの効果を打ち消すように阻害していることが判明しました(対照群の中では何も悪さはしていません)。
これらの結果が、論文中で述べている 「最適自家がんワクチン(AFTV)セット」(Optimum AFTV Set)の開発につながりました。
以上の慎重な背景因子の影響の解析の結果、判明したのが、「最適自家がんワクチンセット」療法を受診された方々の、遠隔転移検出時を起点にした、亡くなるまで(または観察打ち切りまで)の全生存期間の「中央値」が、
なんと! 12.85年 ($)
もありました。
乳がんステージIVの患者群でこれほど長い「中央値」を示した学術論文は、世界でも前例がなく、前回のトピックスNo.649で述べた内容のタイトルどおり、
「達成!世界新記録:“自家がんワクチン”、転移した乳がんで世界最長の延命効果を示す」
だったのです。
おっと、まだ続きがあります。
・この値($)を何と比較したのか、
・AFTVとRTを併用しても、(この組み合わせは今回のトピックスのトップにある“イムラジ”になっていますよ!)重大な副作用は見られない
というが、どんなデータがあるのか、という点について、次号のトピックスNo. 651で解説します。
お楽しみに!
Reference
1. Kuranishi F, Miyazaki T, Tagashira T, et al.
Thirty-five-year follow-up real-world data revealed the efficacy of autologous formalin-fixed tumor vaccine on metastatic breast cancer – A target trial emulation.
Clinical Breast Cancer
Available online 27 June 2025
In Press, Journal Pre-proof
https://doi.org/10.1016/j.clbc.2025.06.008
~~~△▲~~~△▲~~~
より長く生きられるという安心感を!
You Tubeで【自家がんワクチンとは】をご覧ください。
~~~△▲~~~△▲~~~